「生成AIに指示を出しても、ありきたりな答えしか返ってこない…」そんな風に悩んでいませんか?
生成AIの回答の精度に関する悩みは、指示の出し方である「プロンプト」を少し工夫するだけで解消される可能性が高いです。意図が伝わりにくいプロンプトでは、高性能な生成AIが十分に力を発揮できないからです。
本記事では、生成AIのプロンプトに関する以下のトピックについて解説します。
- プロンプトの基礎知識
- プロンプトのコツ
- 代表的なプロンプトのテンプレート
本記事の内容をとり入れることで、プロンプトの精度が高まり、生成AIのアウトプットに悩む機会が減るでしょう。
生成AIのプロンプトとは
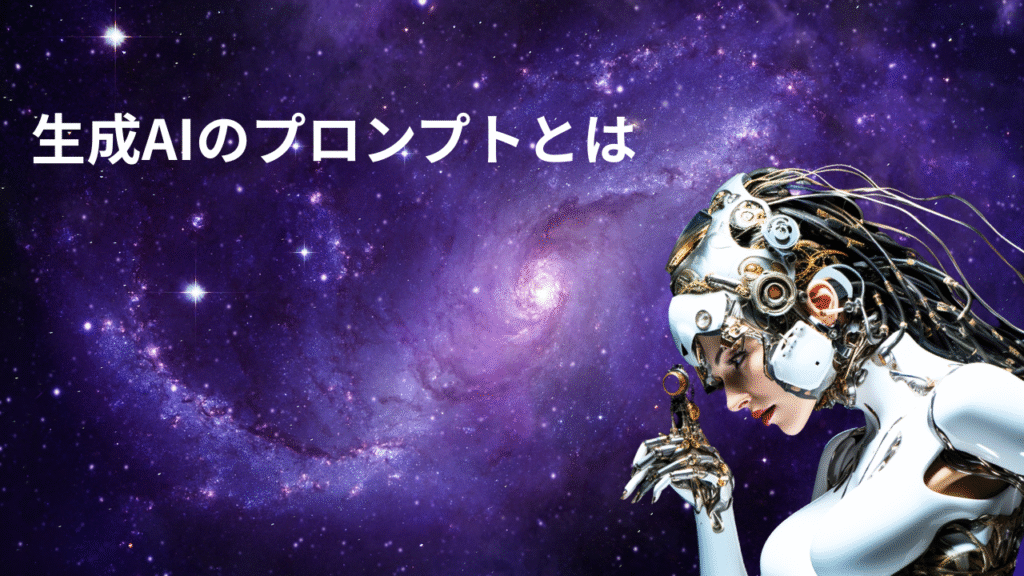
プロンプトとは、生成AIに対して「何をしてほしいか」を伝えるための指示文や命令文のことです。
生成AIは、プロンプトの内容に基づいて文章やアイデアなどを生成するため、プロンプトの良し悪しがアウトプットの質に大きく影響します。
たとえば、「〇〇に関するブログ記事を書いて」のように、曖昧で不明瞭なプロンプトでは、意図通りのアウトプットは難しいです。
プロンプトの内容次第で、高性能な生成AIを有効活用できるか決まります。精度の高いプロンプトを作成するスキルは、今後のWebライターにとって不可欠と言えるでしょう。
生成AIのプロンプトのコツ8選
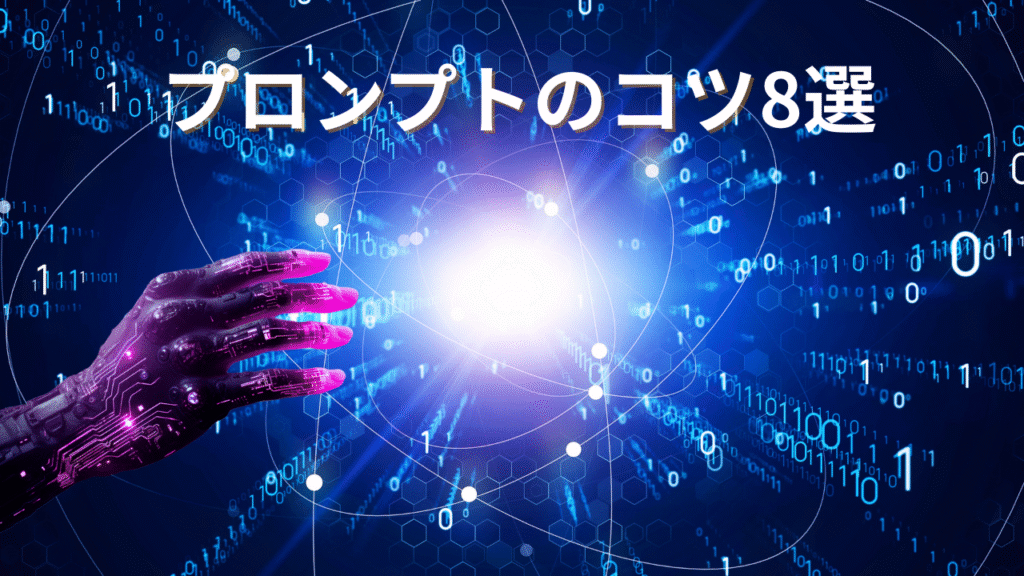
この章では、生成AIのアウトプットの質を高めるためのコツを8つ紹介します。これらのコツをマスターすれば、あなたのライティング業務は劇的に効率化するでしょう。
1. 生成AIに役割を与える
生成AIに「あなたは〇〇の専門家です」といった具体的な役割を与えることで、生成される文章の質と専門性が格段に向上します。
なぜなら、役割を与えることで、生成AIはどのような知識や視点をもとに回答すれば良いのかを理解できるからです。
あなたはプロのSEOコンサルタントです。顕在ニーズと潜在ニーズの違いをWebライティング初心者にわかりやすく教えてください。
上記の例では、SEOコンサルタントという役割を指定しているので、SEO関連の知識を重点的におさえた回答が期待できます。
2. 記事の目的とターゲットを明確に伝える
プロンプトに記事の目的とターゲットを設定することで、生成AIはゴールと読者像を理解しやすくなります。
目的やターゲットが曖昧なままだと、生成AIはどのような内容で回答すれば良いか判断できず、抽象的で的を射ない文章になってしまう可能性が高いです。
あなたはプロのWebマーケターです。KW「Webマーケター 向いている人」でのSEO記事を作成してください。
#目的
自社のWebマーケティング講座を訴求する
#想定読者
・Webマーケティング職に興味がある社会人
上記のように目的や想定読者を決めることで、Webマーケティング職に興味がある人に適した情報や言葉を盛り込み、自社のサービスを訴求した記事の出力が期待できます。
3. 具体的でわかりやすい指示を出す
生成AIは行間が読めずユーザーの真意を掴めない場合もあるので、プロンプトが曖昧だと期待通りの結果を得られない場合があります。
具体的でわかりやすいプロンプトにすることで、的確で適した構造の結果を得やすくなるでしょう。
あなたは最新の生成AI事情に詳しいWebライターです。生成AIの具体的な活用事例についての記事を作成してください。
#想定読者
・生成AIで業務を効率化したい経営者
#読者の背景
・競合他社は生成AIで業務効率化をしているので、焦りを感じている
・生成AIで無駄を省いてコストカットしたい
・できるだけ簡単に生成AIを導入して、低コストで運用したい
#出力形式
・真面目で堅実なトーン
・文字数は5000文字程度
具体的でわかりやすいプロンプトにするコツとしては、以下のポイントが挙げられます。
- 5W1Hを盛り込む
- 出力形式を指定する
- 必要な情報と不要な情報をわける
上記のように具体的で明確な指示を出すことで、生成AIの性能を最大限に引き出して自分が求めている情報を得やすくなります。
4. 一度に多くのタスクを要求しない
生成AIへ一度に多くのタスクを要求すると混乱してしまい、いずれの要求も十分に満たせない結果になる可能性が高まります。
一つのプロンプトに多くの異なるタスクや複雑な条件を詰め込みすぎると、生成AIは指示を正確に解釈できずに出力の質が低下するからです。
たとえば、「新商品のマーケティング戦略の立案とキャッチコピーの提案、SNS投稿文も考えて」など一度に多くのタスクを要求するのはやめ、以下のようにシングルタスクにしましょう。
新商品Aについてのマーケティング施策を行いたいと考えています。プロのWebマーケターとして、ターゲット顧客を分析してください
また、記事作成時も一度にすべてを出力させようとすると精度が下がりやすいので、H2ごとなど分割しながら記事を作成するのがおすすめです。
5. 条件や手順を指定する
プロンプトに条件や手順を指定することで、生成AIのアウトプットの質が安定しやすくなります。
なぜなら、出力形式をコントロールしたり、生成AIの思考を適切に誘導できたりするので、的外れな回答が出にくくなるからです。
簡単なタスクを依頼する場合は、条件や手順にこだわらなくてもそれなりの回答は期待できますが、複雑なタスクは多くの場合で条件や手順を指定するのがベターと言えるでしょう。
あなたはプロのWebライターです。KW「Webライター 将来性」で、読者ニーズを満たすSEO記事の構成を作成してほしいです。
#手順
1.検索上位10記事の記事構成やサジェストワード、再検索ワードなどで読者ニーズを把握する。
2.読者が知りたい順番でスムーズに読み進められるように、読者ニーズを満たした構成を作成する
#条件
・想定読者は、生成AIの普及でWebライターを始めていいか迷っているWebライティング未経験者
・構成に含めてほしいトピックは、Webライターの将来性がある理由と、不安視される理由
・想定文字数は7000文字
複雑で高度な回答を期待する場合は、上記のように手順や条件を指示することで、期待通りの結果が得やすくなるでしょう。
6. 「#」や「”」などの記号を効果的に使う
プロンプトに「#」や「”」といった記号を効果的に使うことで、AIへの指示がより明確になり、回答の精度が向上します。
記号は、プロンプト内の情報を構造化し、AIが意図を正確に解釈するための手助けとなるからです。
よく使われる記号と活用例は以下のとおりです。
| 記号 | 主な役割と活用例 |
|---|---|
| #, ## | 見出し: プロンプト全体をセクションにわけ、構造を整理します。「#」が大見出し、「##」が中見出しといった階層で使われます |
| “”” | 複数行の引用: 長い文章や例文、コードなどを一つのブロックとして明確に区切ります。プロンプトの可読性も向上します |
| -, * | 箇条書き: 複数の項目や要点を整理して伝える際に使用します |
| : | 項目の定義: 「目的:」「ターゲット:」のように、特定の要素を定義し、AIに要求内容を理解させやすくします |
| { } | 変数: テンプレートを作成する際に、ユーザーが入力する部分を {名前} のように変数として示します |
これらの記号を適切に活用できれば、生成AIの解釈精度が向上して、複雑なタスクでも的確な回答が出力されやすくなるでしょう。
7. 出力見本を示す
プロンプト内に「こう出力してほしい」という見本を添えると、生成AIはそのパターンを模倣しやすくなり、形式・文体・情報量が揃った回答を得やすくなります。
{URL}の記事の内容を、出力見本のような形式で要約してください。
#URL
https://hightechnician.cfd/blog/writer-future/
#出力見本
記事のポイント:
– ①プロンプトとは生成AIへの指示文のこと
– ②生成AIの回答精度を高めるにはプロンプトが重要
– ③有名なプロンプトのテンプレートには「深津式」がある
記事を読むベネフィット:
生成AIのプロンプトの精度を高める具体的なテクニックが身につき、生成AIを有効活用できるようになる
出力見本は必須ではないですが、少ない手間で回答の精度や一貫性を引き上げられる有効なテクニックなので、覚えておいて損はないでしょう。
8. プロンプトをブラッシュアップして再生成する
プロンプトに工夫を凝らしたとしても、生成AIが最初から理想通りの回答をするのは多くありません。
最初から100点の回答を得ようとせず、まずは70点レベルの回答を目指して、悪い部分を直していく姿勢が大切です。
返ってきた回答をもとに「〇〇の部分をもう少し具体的にして」「この視点が足りない」とフィードバックを送ることによって、徐々に回答の精度が上がります。
回答の問題点が見当たらなくてもブラッシュアップできないか検討したい場合は、以下のように生成AIにプロンプトの問題点を聞いてみるのもおすすめです。
先ほどのプロンプトが70点だったとして、100点にするにはどう改善すれば良い?
生成AIとの壁打ちを繰り返しながらプロンプトを修正していくことで、アウトプットの質は着実に高まっていくでしょう。
代表的なプロンプトのテンプレート「深津式」を紹介

プロンプトのコツは理解できたものの、「毎回自分で細かく指示を考えるのは、正直ちょっと面倒だな…」と感じていませんか?
そんな方には、プロンプトのテンプレートを活用して効率化するのがおすすめです。
この章では、代表的なプロンプトのテンプレートである「深津式」の基本情報や、メリット・デメリットなどを解説します。
深津式プロンプトとは
深津式プロンプトとは、note社のCXOである深津貴之氏が考案した、AIへの指示を構造化するためのテンプレートです。
深津式プロンプトは、基本的に「対象」「条件」「構造」「敬語」の4つの要素を組み合わせた構成のプロンプトを作成します。
具体的には、以下のように「#」などの記号を使ってセクションを設け、複数の要素を箇条書きで記入していくスタイルが一般的です。
#命令書: 生成AIに与える役割(対象)などを記述する
#制約条件: 文字数やその他の条件、敬語などを記述する
#入力文: 要約したい文章や、記事のテーマなど、AIに処理させたい内容を入力する
#出力文: この後にAIが回答を生成するように促す
テンプレートを用いることで、プロンプトを一から考えなくても一定水準以上の結果が得られやすくなります。
深津式プロンプトのメリット・デメリット
深津式プロンプトのメリット・デメリットは以下のとおりです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・一定水準以上の回答が期待できるプロンプトを効率よく作れる ・テンプレート化されているので初心者でも作成しやすい ・さまざまな文脈やタスクに対して適用できる | ・プロンプトがシンプルすぎるため、複雑なタスクには不向き ・テンプレートに依存しすぎると、プロンプトを作成する創造性が養われない ・AI技術は急速に進歩しているため、深津式テンプレートが使用しにくくなる懸念もある |
深津式テンプレートを活用すると、生成AI初心者でも簡単にプロンプトを作れるのが魅力です。
深津式以外にも「七里式」や「ゴールシーク」など、さまざまなプロンプトテンプレートがあるので、用途に応じて使いわけたい方は他のテンプレートも調べましょう。
深津式について詳しく知りたい方は、テンプレートを考案した深津さん自身が執筆した以下の本がおすすめです。



コメント