「LLMOって最近よく聞くけど、何のことだろう」
「SEOからの流入が減ってなんとかしたい…」
「LLMOが主流になるからSEOは必要ないのかな」
このような疑問や不安を抱えるWebマーケティング担当者や個人ブロガーの方も多いのではないでしょうか。
ユーザーの情報収集の方法が大きく変わろうとしている2025年現在、従来のSEOだけでなく、生成AIに自メディアの情報を的確に引用してもらうための新しいアプローチが不可欠になっています。その鍵を握るのが「LLMO(大規模言語モデル最適化)」です。
本記事では、LLMOに関する知識が浅い人でも簡単に理解できるように、以下の内容をわかりやすく解説しています。
- LLMOの基礎知識
- LLMOとSEOの違い
- LLMOの対策方法
- LLMO対策をする際の注意点
本記事を読めば、生成AI時代の変化の波を乗りこなし、未来のアクセスを獲得するための確かな一歩を踏み出せるでしょう。
LLMOとは?

LLMOとは、生成AIが回答する際に、運営している自メディアの記事が引用されやすいように最適化する施策のことです。
この章では、LLMOを理解する上で重要な以下の3点を解説します。
- LLM(大規模言語モデル)の基礎知識
- LLM(大規模言語モデル)とLLMOの関係性
- LLMOが注目されている理由
LLM(大規模言語モデル)とは
LLM(大規模言語モデル)とは、膨大な量のテキストデータとディープラーニング(深層学習)技術を用いて構築された、高度なAI技術です。
従来の自然言語モデルと比べて「計算量」や「データ量」などが大幅に増強されたことから、大規模言語モデルと呼ばれています。
ChatGPTのようなLLMを活用したサービスは、チャットを通して自然な会話ができ、さまざまなタスクを高精度かつ高速で行えることから、世界中で話題になっています。
LLM(大規模言語モデル)とLLMOの関係性
| 項目 | LLM (大規模言語モデル) | LLMO (大規模言語モデル最適化) |
|---|---|---|
| 定義 | 膨大なテキストデータを学習し、人間のように文章を理解・生成できるAIモデルのこと | LLMに対して自社情報を誤解なく、正確に理解・出力させるための最適化手法 |
| 目的 | 自然言語処理を行い、ユーザーへの質問応答や文章生成など多様な言語タスクを実行する | 生成AIが自メディアの情報を引用・参照してもらい、生成AI利用者からの流入を促す |
| 具体例 | ChatGPT、Gemini、Claudeなど | 自メディアのFAQを構造化し、AIに誤解なく伝わるようにするなど |
LLMとLLMOは技術と活用施策という関係にあり、LLMを利用している生成AIに対して、自メディアの情報を効果的に認識・参照させるためのマーケティング施策になります。
たとえば、以下の画像はPerplexityという生成AIがインターネット上の情報を参照してLLMOについて解説した文章です。
赤枠で囲った数字は参照した記事のリンクとなっており、LLMOとは上記のように生成AIの回答時に自メディアが参照されるように目指していくイメージです。
LLMOが注目されている理由
LLMOが注目されている理由としては、生成AIの爆発的な普及に伴って、ユーザーの検索方法が多様化し始めているからです。
以下の画像はGoogleで「LLMOとは」というキーワードで検索した際に、検索順位トップの記事の上に出てきた生成AIによる解説文です。
上記はGoogleが2024年頃から実施を始めた「AI Overview」というサービスで、ピンときた方は多いと思います。
厳密にいうとGoogle検索の際に自動的に生成される文章で引用・参照されるための対策はGEOと呼び、LLMOと異なる部分もあります。ですが、生成AIでの回答時に自メディアを露出させようという目的は同じです。
今後はSEOでの検索流入が減少する可能性が高く、自メディアへの流入数を確保するためにも、生成AIの回答時に自メディアが引用・参照されることが大切なのがわかるでしょう。
LLMOとSEOの違い
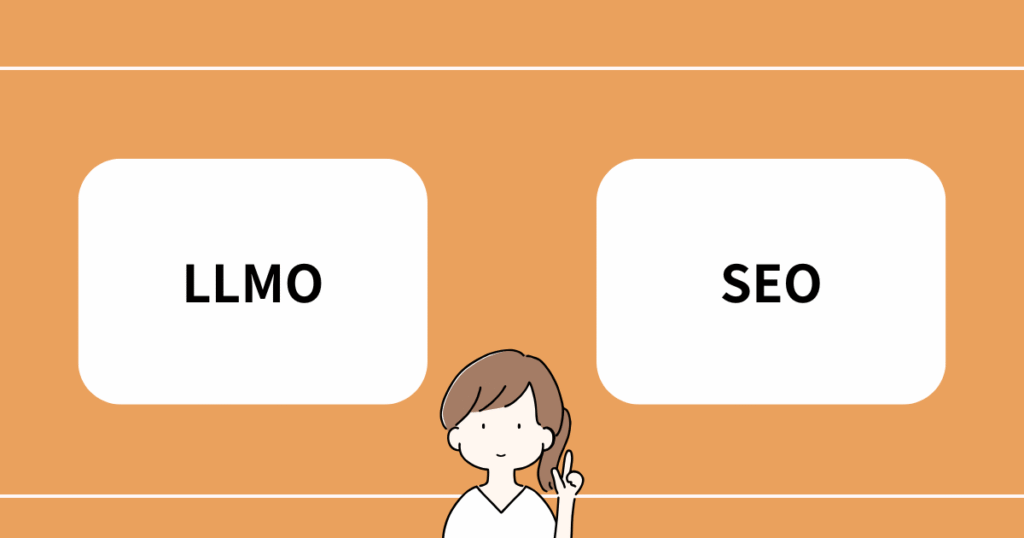
LLMOとSEOは、どちらもユーザーの検索行動時に自メディアへの流入を促すための最適化を目指す施策ですが、以下のように最適化対象やアプローチは異なります。
| 項目 | LLMO | SEO |
|---|---|---|
| 最適化対象 | ChatGPT、Geminiなどの生成AIやGoogle検索時のAIによる概要など | Google、Bingなどの検索エンジン |
| 目的 | 生成AIの回答時に自メディアの情報を引用・参照させて、ブランド認知度や専門性を高める | 検索結果での上位表示によるクリック数・サイト流入数の最大化を目指す |
| 評価基準 | ・生成AIが学習、参照しやすいか ・情報の信頼性 | Googleのアルゴリズム(E-E-A-Tや被リンクなど) |
| 効果的なアプローチ | ・生成AIが理解しやすい明確な情報にする ・一次情報を入れる ・構造化データの実装 | ・適切なキーワード選定 ・読者ニーズを満たしたコンテンツ作成 ・内部リンクの強化 ・被リンクの獲得 |
| 成果指標 | ・生成AI回答時の引用、露出回数の増加 ・指名検索数の増加 ・生成AI経由のサイト流入数増加 | ・検索順位上位獲得によるPV数、CVRの増加 ・ブランド認知の拡大 |
LLMOとSEOは対立するものではなく、似ている部分も多いです。それぞれの特性を理解しながら、バランスよく両立させていくことが大切です。
次の章では、LLMOの具体的な施策方法を解説します。
LLMOの対策方法

LLMO対策は、すぐにできる短期的な施策と、自メディアの将来的な成長を見据えた中長期目線での施策があります。それぞれ詳しく解説します。
短期のLLMO施策
すぐに実践できる短期的なLLMO施策から紹介します。
llms.txtを設置する
llms.txtとは、生成AIに対して「このサイトの情報を学習に使っていいですよ」という意思を示すための特別なファイルのようなものです。
llms.txtを通じて、生成AIがWebサイト情報を利用する際のルールを、運営者側で明示できるのが大きな特徴です。
WordPressを使用している方であれば、「Website LLMs.txt」というプラグインを導入すれば、簡単にllms.txtを設置できます。
WordPress以外でWebサイトを運用している方は、「llms.txt」という名前のファイルをサイトのルートディレクトリに設置し、学習を許可するページや条件などを記載します。
llms.txtを設置しているWebサイトはまだ多くないので、今のうちから設置しておくことで、先行者利益を獲得できるかもしれません。
構造化データを実装する
「構造化データを実装する」とは、Webサイトに書かれている情報を生成AIが正確に理解できるように、専用の形式で読み込ませる作業のことです。
構造化データを実装するのが重要な理由は、生成AIがあなたのサイトの情報を正確に理解し、「これは信頼できる情報源だ」と認識しやすくするためです。
構造化データを適切に実装することで、生成AIが回答する際に、あなたのサイトの情報が引用される可能性が高まります。
WordPressでWebサイトを運用している方であれば、「Yoast SEO」などのプラグインを導入すれば、簡単に構造化データを実装できます。
生成AIに正しく情報を理解してもらうためにも、構造化データの実装も欠かせない施策と言えるでしょう。
中長期のLLMO施策
短期的な施策と合わせて、Webサイトそのものの価値を高めていく中長期的な目線でのLLMO対策も非常に重要ですので、参考にしてください。
SEOで成果を出す
「LLMOの時代になったら、もうSEOはやらなくてもいいの?」と思うかもしれませんが、そんなことはありません。
なぜなら、ユーザーや検索エンジンにとってわかりやすいサイト構造や論理的な文章は、生成AIにとっても理解しやすいからです。
たとえば、見出しの構成を整理したり、関連性の高いページを内部リンクで繋いだりといった基本的なSEO対策は、そのままLLMOにもよい影響を与えます。
SEOは「検索で見つけてもらうための最適化」、LLMOは「AIに正しく引用してもらうための最適化」と考えると、両方をバランスよく進めることがいかに大切なのかがわかるでしょう。
Webサイト全体で権威性と信頼性を高める
生成AIは「誰がその情報を発信しているのか?」という、サイトの権威性や信頼性を非常に重視します。
これは、Googleが提唱するE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の考え方と全く同じで、信頼できる情報源から回答を生成しようとするAIの性質によるものです。
権威性や信頼性を高めるためには、以下のような方法が考えられます。
- 運営者情報を詳しく明記する
- その分野の専門家が書いた記事であることを示す
- どんな経験に基づいた情報なのかを具体的に記述する
上記のような地道な努力を積み重ねて信頼性や権威性を高められれば、LLMOだけでなくSEOでの効果が高まるでしょう。
自メディアが外部からたくさん言及されるようにする
自メディア内の施策以外にも、他のサイトからどれだけ自メディアが言及されているかも生成AIからの評価に影響します。
生成AIは情報の信頼性や権威性を判断する際に、自メディア内の情報だけでなく、外部からの客観的な評価も重視するからです。
具体的には、信頼性の高いニュースサイトや業界の専門家ブログなどで好意的に紹介されると、生成AIは自メディアを信頼性が高いと判断しやすくなります。
自メディアが外部から言及されるようにするには、以下のような施策が有効です。
- 独自の調査や統計データをまとめたレポートを公開する
- 業界の専門メディアに寄稿したり、専門家としてインタビューやコメントを提供したりする
- 企業の重要な取り組みなどをプレスリリースとして配信し、ニュースメディアに取り上げてもらう
- 第三者が運営するレビューサイトや比較サイトで高い評価や推奨を得る
プレスリリースを配信したり、業界メディアに記事を寄稿したりと手間はかかりますが、SEOでの被リンク戦略と同様に、外部からの評価を高めることはLLMOとSEOの両方に効果があります。
記事に一次情報を積極的に入れる
生成AIは検索エンジンと同様に、権威性や信頼性以外にも独自性のあるコンテンツを重視する傾向があります。
なぜなら、大規模言語モデル(LLM)が学習したインターネットの膨大な情報の多くは、二次情報や三次情報だからです。そのため、他にはない独自の価値を持つ一次情報のある記事は、検索エンジンだけでなく生成AIにも高く評価される傾向があります。
一次情報とは、以下のようにそのサイトでしか得られないオリジナルの情報のことです。
- 自社で実施したアンケート調査の結果
- 商品を実際に使った人の詳細なレビュー
- 専門家への独自インタビュー
読者の満足度を高めるだけでなく、生成AIからも選ばれるための強力な武器として、一次情報の活用を意識しましょう。
LLMO対策する際の注意点
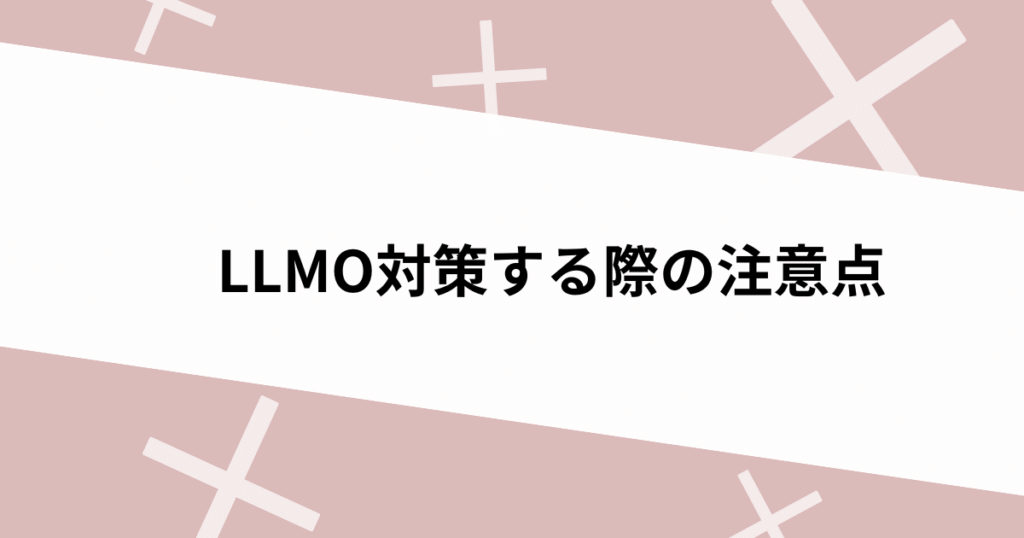
今後は生成AIで情報収集する流れが加速することが予想されるので、早くからLLMO対策すれば有利になる可能性が高いです。
しかし、闇雲にLLMO対策を始めると「思ったような成果が出ない…」となる懸念もあるので、LLMO対策の注意点も確認しましょう。
効果測定が難しい
LLMOの最大の課題ともいえるのが、施策の効果を正確に測りにくい点です。LLMOは比較的新しい分野であり、多くのマーケティング担当者がLLMOの効果をどのように測ればよいかという実践的な課題に直面しています。
なぜなら、従来のSEOのように検索順位やクリック数といった明確な指標がなく、生成AIがどのように情報を引用したかを直接的に知る手段がまだ確立されていないからです。
また、AIが生成した回答だけで満足するユーザーも多く、LLMO対策をしても自メディアへのアクセスにつながるとは限りません。
まだ発展段階にありますが、LLMOの効果測定方法としては以下のような手段が挙げられます。
- GA4の「セッションの参照元/メディア」から生成AIの流入数を確認
- Profoundなどのモニタリングツールを用いる
- 自メディアの指名検索が増えているか確認
これらの指標を時系列で比較して、施策の前後でどのような変化があったかを分析することが、LLMOの効果を把握する上で重要となるでしょう。
LLM(大規模言語モデル)のアルゴリズム変動によってLLMO対策の効果が安定しない懸念もある
LLM(大規模言語モデル)は継続的に開発・更新されており、モデルのバージョンアップや学習データの変更によって、情報の参照元や回答の生成ロジックが変わる可能性もあります。
Googleのアップデートよりも生成AIのアルゴリズム変動のほうがスピードが早く、昨日まで有効だったLLMO対策が、今日には通用しなくなる懸念も十分あるでしょう。
また、LLMO対策の対象となる生成AIは一種類だけではありません。インターネットに接続してリアルタイムの情報を参照するモデルと、固定データセットで学習した自己完結型のモデルでは、情報の参照方法が異なります。
そのため、あるAIで効果があった施策が、別のAIでは通用しない可能性もあることには注意が必要です。
このような変動リスクがあるため、LLMOは特定のアルゴリズムの攻略を目指すのではなく、より本質的で普遍的なアプローチが求められるでしょう。
具体的には、本記事のLLMO対策の中長期目線での施策で紹介した、権威性や信頼性の高いWebサイトにしたり、記事内に一次情報を充実させたりするのが大切です。
LLMO対策には専門知識が必要な場合がある
「LLMOって、なんだか専門的で難しそう…」と感じるかもしれませんが、その感覚はあながち間違いではありません。
LLMOは新しい分野であり、効果的な施策を行うには、生成AIの仕組みや構造化データといった技術的な知識を求められる場面があるからです。
社内や周りに詳しい人材がいない場合は、新しく学んだり、場合によっては外部の専門家に依頼したりする必要が出てくるかもしれませんね。
ただし、多くのLLMO対策は従来のSEOの延長線上にあるという意見が多いため、すべてのマーケターがAI開発者レベルの知識を持つ必要はありません。
まずは本記事で紹介したような基本を押さえ、最新情報をキャッチアップしながら柔軟にLLMO対策をアップデートしていく姿勢が大切です。
LLMO関連のよくある質問

LLMO関連のよくある質問4つに回答します。
LLMOが主流になりつつあるので今後はSEOを学ぶ必要はないですか?
結論からいうと、LLMOの時代になっても、SEOの知識やスキルは重要です。
なぜなら、中長期目線のLLMO施策の多くは、E-E-A-Tの強化したり、記事内の一次情報を充実したりするなど、SEOの基本的な考え方に基づいているからです。
LLMOとSEOは対立するものではなく、両方をバランスよく進めることが、今後のWebサイト運用の鍵となるでしょう。
LLMO対策をするとどれくらいで効果が出ますか?
効果的なLLMO対策をすれば、一般的には3か月から6か月程度で何らかの効果が現れ始めるといわれています。
Webサイトの信頼性や情報の質が生成AIに評価され、学習データに反映されるまでには一定の期間が必要だからです。
成果を焦らずに、生成AIやユーザーにとって価値のある情報を地道に発信し続けることが、遠回りのようで一番の近道です。
GEOやAIOはLLMOとどのような関係がありますか?
LLMOやGEO、AIOなどはすべて「AIに情報を最適化する」という大きな目的を共有する、兄弟のような言葉だと考えるとわかりやすいです。
ただし、それぞれの言葉が指す範囲には、以下のように違いがあります。
| 用語 | 最適化する対象 | 最適化対象のイメージ |
|---|---|---|
| AIO | AIシステム全般 | 最も広い概念で、検索エンジン搭載のAIやAIチャットボット、AIを活用したプラットフォームなどのAI全般 |
| GEO | 生成AI搭載の検索エンジン | Googleの「AIによる概要」などが対象 |
| LLMO | 大規模言語モデル(LLM) | ChatGPTなどの、AIモデルそのものが対象 |
言葉の違いに惑わされず、まずはユーザーとAIの両方にとって価値あるコンテンツを作る、という基本を大切にしましょう。
中小企業のサイトや個人ブログでもLLMO対策は必要ですか?
LLMOは、リソースが限られている中小企業や個人ブログにこそ、大きなチャンスをもたらします。
LLMOで重視されるのは会社の規模や広告費の大きさではなく、「情報の質と信頼性」だからです。
大手企業にはない独自の視点や、ニッチな分野での深い専門知識、あるいは自社でしか語れない体験談といった「一次情報」は、生成AIから高く評価される傾向にあります。
また、LLMO対策を始めている企業は多くなく、早めに取り組むことで中小企業や個人ブログでも先行者利益を狙うことが可能です。



コメント