「生成AIの進化でWebライターの仕事がなくなるのでは?」と危惧している方もいるかもしれません。
結論から言うと、一部の単純作業の案件は少なくなる可能性が高いですが、生成AI時代に必要なスキルを磨くことで、今後もWebライターとして活動していくことは可能です。
生成AIを効果的に活用するスキルがあれば、執筆速度を1.5倍以上にすることが可能なので、生成AIの普及をネガティブに考えるのはもったいないと思います。
本記事では、Webライターの生成AI活用に関する以下の内容を解説しています。
- 主要な生成AIの紹介
- 生成AIを活用して執筆作業を効率化する方法
- AIライティングの案件を継続的に受注するための戦略
- 生成AI活用時の注意点
- 生成AI時代Webライターに求められるスキル
生成AI時代もWebライターとして活躍したい方は参考にしてください。
主要な生成AIの紹介
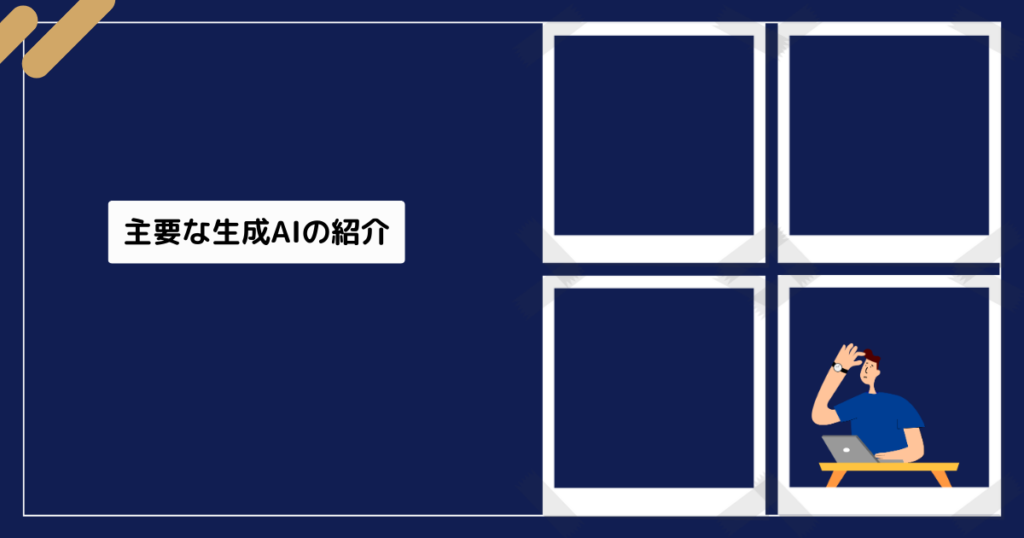
2025年5月現在で、主要な生成AIの特徴をまとめました。
| ツール名 | 提供元 | 主な特徴 | 料金プラン (月額) | 主な用途 |
|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | OpenAI | GPT-4oシリーズ(テキスト・画像・音声対応)や最新モデルGPT-4.5、推論モデルのGPT-o3など多様なモデルを搭載。感情知能向上、誤情報低減。リアルタイムWeb検索や画像解析も可能など汎用性が高い | ・無料プラン ・Plus:$20 ・Pro:$200 ・Team:$25 ・Enterprise :(要問い合わせ) | ・文章生成 ・対話、応答 ・アイデア出し ・画像生成 ・画像の認識、解析、解説 ・情報収集、要約 ・コード生成 |
| Gemini | マルチモーダル対応(テキスト・画像・音声・動画)。Googleサービスとスムーズに連携できるので、情報収集や資料作成などの業務効率を向上できる。高度な安全対策が施されており、サイバー攻撃や自律性のリスクに対する包括的な安全性の評価が高い | ・無料プラン ・Pro:2,900円 | ・文章やリストの作成 ・情報の検索 ・アイデア出し ・画像の認識、解析、解説 ・テキストの要約、翻訳、校正 ・論文や数学の問題解説 ・コード生成 ・Googleアプリとの連携 | |
| Claude | Anthropic | 人間の感情やニュアンスに配慮した、自然な文章生成が得意。 安全性・倫理性重視で法務・医療分野にも適用しやすい。 最大20万トークン(約15万文字)以上の多くの情報を一度に処理できるので、長文の読解、要約、分析に適している | ・無料プラン ・Pro:$17 ・Team:$25 ・Max:$100 ・Enterprise :(要問い合わせ) | ・文章生成 ・コンテンツ制作 ・長文処理 ・要約、翻訳 ・分析 |
| Microsoft Copilot | Microsoft | Microsoft365と連携し、文章生成やメール要約、Excelグラフ作成、PowerPoint資料作成などを効率化できる。 OpenAIのGPTモデル(GPT-4、GPT-4 Turboなど)を基盤としている | ・無料プラン ・Pro:3,200円 (Microsoft365必須) | ・文章生成 ・ビジネス文書作成 ・Excelでのデータ集計、分析、グラフの自動生成 ・PowerPointでのプレゼンテーション資料の骨子作成やデザイン提案 |
| Perplexity | Perplexity AI, Inc | 最新のインターネット情報からの情報収集に強みをもち、ファクトチェックが得意。回答に情報元を明示していて信頼性が高い。 | ・無料プラン ・Pro:$20 | ・最新の情報収集 ・ファクトチェック ・文章生成 ・画像生成 |
| Notion AI | Notion Labs, Inc | SNSの投稿、議事録、会議のアジェンダなどさまざまな形式の文章の生成機能を搭載。 ノートアプリ内で文章作成、要約、情報整理が可能。既存データベースとの連携で企業のナレッジ活用に強みをもつ。 | ・無料プラン(20回まで) 有料 プラン:$10 | ・多様な形式の文章の作成 ・情報整理 ・要約 ・ビジネスでの業務効率化 |
2025年5月現在は、生成AIが進化していることもあり、どのツールを使用しても基本的な文章品質は高いです。
ツールの選び方に迷うかもしれませんが、文章生成を中心での利用を考えているなら、人間らしい自然な文章を生成できる「Claude」がおすすめです。また、リサーチ中心での利用なら、「Perplexity」をおすすめします。
自身の状況によって最適な生成AIは異なるので、上記の表や口コミなどを参考にして、使用する生成AIを選択しましょう。
Webライターが生成AIを活用して執筆作業を効率化する方法
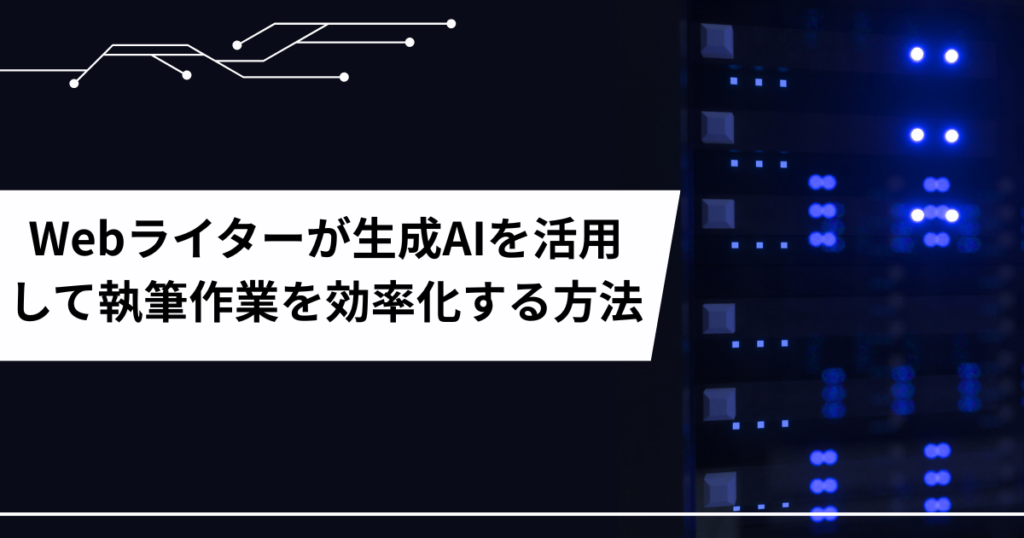
Webライターはクライアントにキーワードを選定されるケースが多く、執筆作業のプロセスは以下の3工程に分けられる場合が多いです。
- 構成作成
- 執筆
- 校正とファクトチェック
各工程ごとに、生成AIをどのように活用できるのかを詳しく見ていきましょう。
構成作成の工程
記事構成を生成AIで作成する際は、「KW『Webライター ai活用』で記事構成を作成して」のような曖昧な指示ではなく、具体的なプロンプト(生成AIへの指示文)を入力するのが大切です。
なぜなら、記事の想定読者や検索意図、検索上位の記事構成などの情報をプロンプトに入力することで、出力する構成の精度が高くなるからです。
効率よく生成AIに検索上位の記事構成の情報を渡したい場合は、ラッコキーワードの見出し抽出機能の使用をおすすめします。
見出し抽出機能で検索上位の構成をcsv形式でダウンロードした後に、生成AIのプロンプト入力時にアップロードすれば、検索上位の構成の情報を渡せます。
ただし、生成AIが出力した記事構成は読者ニーズの理解があまかったり、余計な見出しがあったりします。生成AIを過信しすぎずに、自分でチェックして、問題点があれば修正するのが大切です。
生成AIのプロンプトのコツについて知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
生成AIプロンプト作成のコツ8選!思い通りの回答を引き出す方法を紹介
執筆の工程
構成の工程と同様に、執筆の工程でも生成AIへのプロンプトは具体的にして、文章の出力後に人間での手直しをすることが大切です。
また、一度にすべての構成の執筆を生成AIに頼んでしまうと、出力する文章の精度が下がる傾向にあります。そのため、H2ごとなど段階的に執筆してもらうのをおすすめします。
以下は具体的な執筆依頼時のプロンプト例です。
あなたはSEOコンサルタント顔負けのプロのWebライターです。以下の見出しの執筆をしてください。
H2 〇〇
H3 〇〇
H3 〇〇
H3 〇〇
#テーマ
Webライターの生成AIの活用方法について
#出力形式
・1つのH3ごとの文字数は200〜300文字程度
・1文ごとに改行する
・文体は「です」「ます」調にする
上記は簡単なプロンプト例です。クライアントのマニュアルがあれば条件を付け足すことで、自分の想定していた文章が生成されやすいでしょう。
校正とファクトチェックの工程
生成AIが事実に基づかない誤情報を生成する現象は「ハルシネーション」と呼ばれ、生成AIがどれだけ進化しても避けられません。生成AIで執筆活動を効率化できますが、ファクトチェックは抜かりなくしましょう。
ファクトチェックをする際は、生成AIをインターネット検索可能なモードにして、最新の情報源から事実誤認がないか確認すると間違いにくいです。
なぜなら、インターネット検索できない状態だと、生成AIが過去の学習データだけを参照してファクトチェックを行うため、古い情報を正しいと誤認するリスクがあるからです。
余裕があれば複数の生成AIを使用して多角的にファクトチェックをすることで、事実誤認のリスクをさらに下げられます。
また、生成AIは校正の精度も非常に高く、以下のようにさまざまな観点から文章をチェックしてくれます。
- 誤字脱字がないか
- 文体やトンマナがおかしくないか
- 文章表現がおかしくないか
- クライアントが指定したレギュレーションを守れているか
ちなみに、校正や推敲をする際は、生成AI以外にもライターに人気の「文賢」というツールもおすすめです。
文賢の評判について知りたい方は、以下の記事を参照してください。
文賢は使えない?評判や口コミを元にメリット・デメリットを多角的レビュー
AIライティングの案件を継続的に受注するための戦略

生成AIの進化に伴い、クラウドソーシングサイトやSNSなどで、AIライティングの案件が増えています。AIライティングの案件をこなせるようになれば、既存のSEO記事の案件が減ったとしても、仕事が受注できずに困ることはなくなるでしょう。
この章では、AIライティングの案件を獲得するための具体的な戦略を紹介します。今後のWebライターとしての活動を続ける際の参考にしてください。
AIスキルをアピールするポートフォリオ作成
AIライティングの案件を獲得するためには、営業用のポートフォリオで、実績に加えてAIスキルをアピールすることが大切です。
たとえば、普段から生成AIの最新情報を収集していることをアピールしたり、生成AIを使用して執筆した高品質な記事を見せたりすれば、AIスキルを認めてもらえるかもしれません。
また、AIライティングを依頼するクライアントは短期間での納品を求める傾向にあるので、生成AIによって作業スピードが向上できていることをアピールするのも効果的です。
AIライティングの案件を獲得するためのクライアントの探し方
AIライティングの案件は、さまざまな場所で見つけられます。クラウドワークスで「AIライティング」と検索すると、30件の案件がヒットしました。
引用元:クラウドワークス
2025年5月現在で、AIライティングの案件はそれほど多くない印象です。しかし、株式会社グローバルインフォメーションの調査によると、AIライティングアシスタントソフトウェア市場は2030年までに年平均8.78%のペースで成長する見込みです。
株式会社グローバルインフォメーションの予想通りに、AIライティング用のツールが順調に普及していけば、AIライティングの案件が増えていくでしょう。
AIライティングの案件は、SEO記事作成以外にも商品紹介文や広告コピー、SNS投稿文などさまざまな種類があります。
クラウドソーシングサイト以外にも、Xで探したり、Google検索して気になったメディアに直接営業したりすれば、AIライティングの案件を獲得できる可能性が高まります。
また、自身が得意な分野に絞って応募することで、作業効率化の面だけではなく専門性もアピールできるので、採用率が高まるでしょう。
案件継続のための品質管理とコミュニケーション
AIライティングの案件を継続するには、他の案件と同様に品質管理とクライアントとのコミュニケーションが大切です。
AIライティングを依頼するクライアントは、依頼したライターが生成AIに任せきりになって、低品質な記事を納品するのを懸念していることが多いからです。
クライアントが提示したレギュレーションを守りつつ、複数の生成AIでファクトチェックをしたり、文章におかしなところがないか確認したりして記事の品質を担保しましょう。
また、生成AIは経験に基づいた見解や洞察などを記事内に盛り込むことは苦手としています。
自分が得意なジャンルを執筆している際は、一次情報を積極的に盛り込むことで、クライアントからの評価は高くなるでしょう。
Webライターの生成AI活用時の3つの注意点
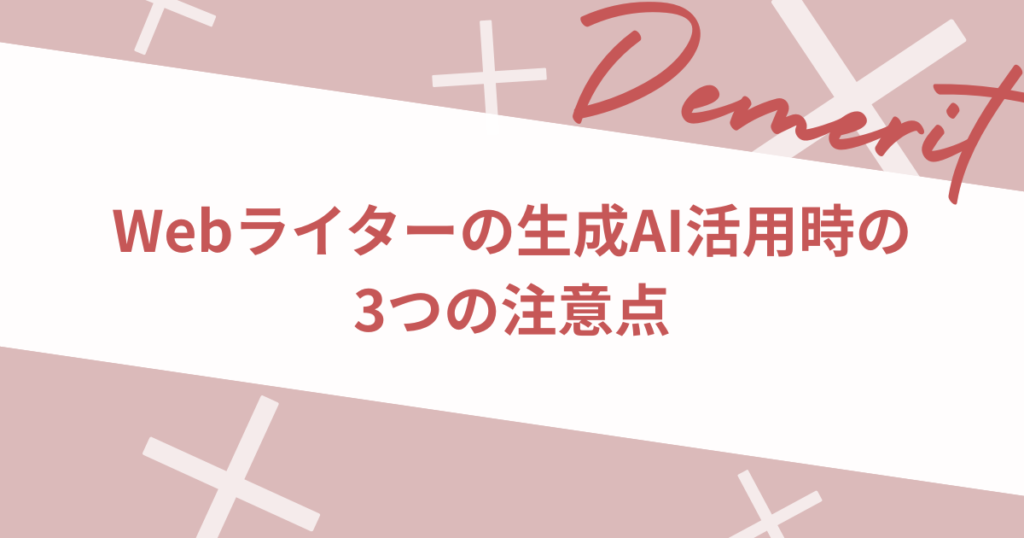
生成AIは執筆作業を大幅に効率化できる便利なツールですが、以下のような注意点もあります。
- 事実に基づかない情報を出力するリスクがある
- 生成AIが出力した文章を使用すると著作権侵害のリスクがある
- AIの活用を禁止しているクライアントも多い
これらの注意点をしっかり理解して対策をとれば、生成AIを安心して活用できるようになるでしょう。
1. 事実に基づかない情報を出力するリスクがある
生成AIは「ハルシネーション」と呼ばれる現象によって、事実に基づかない情報を出力するリスクがあり、利用には十分な注意が必要です。
生成AIがどれだけ進化を遂げてもハルシネーションを完全に避けるのは難しいですが、適切な対策により発生リスクを低減できます。
具体的なハルシネーション対策としては、以下のような方法が挙げられます。
- 出力した文章に参照元のリンクがある場合は、そのサイトからファクトチェックをする
- 複数の生成AIでファクトチェックをする
- 執筆依頼時のプロンプトで、わからないことは「わからない」と答えるよう指示する
ハルシネーションは対策しても発生するという前提で生成AIを使用する必要があるので、上記のようにファクトチェックを徹底的におこなうことが大切です。
2. 生成AIが出力した文章を使用すると著作権侵害のリスクがある
生成AIは普及してから年月がそれほど経っていなく、法整備が整っていません。既存の著作物との間に類似性や依拠性が認められる場合に、生成AIが出力した画像や文章などを無断で公表や販売をすると、著作権侵害になる懸念があります。
令和5年6月に発表された 文化庁の「AIと著作権」で、生成AIの著作権についてさまざまな角度から議論されています。しかし、類似性や依拠性などがケースによって異なるため、著作権侵害の問題はグレーゾーンが多いです。
著作権侵害をしないためにも、以下のような対策をするのがおすすめです。
- 類似性や依拠性を疑われないために、プロンプトで特定のコンテンツを模倣するように指示をしない
- 参照元のサイトを確認して、文章表現が似ていたら修正する
- 各AIツールの利用規約をよく読み、禁止事項や利用範囲を遵守する
便利な生成AIを安全に使用するためにも、上記のように多角的な対策を講じましょう。
3. AIの活用を禁止しているクライアントも多い
生成AIの使用を禁止または制限しているクライアントも多いので、執筆前に生成AIの使用許可を得るようにしたり、案件の応募時に募集内容を確認したりすることが大切です。
クライアントが生成AIの使用を禁止する理由としては、以下のようなリスクがあるからです。
- 誤情報の拡散
- 著作権の侵害
- 機密情報や顧客データの漏洩リスク
- 低品質な記事の納品
生成AIに質問した情報は、AIの学習に利用された後に、他の利用者への回答時に知られてしまうリスクがあるので注意しましょう。
実際にAppleやAmazon、JPMorgan Chaseなどの大企業は、従業員が社内の機密データを外部に流出させる懸念があることから、仕事での生成AIの使用を制限しています。
無断で生成AIを使用すると、バレてしまったときに信頼関係の失墜や契約解除につながる懸念があるため、禁止している場合はクライアントの意向を尊重しましょう。
Webライターの仕事はなくなる?大手メディアの見解
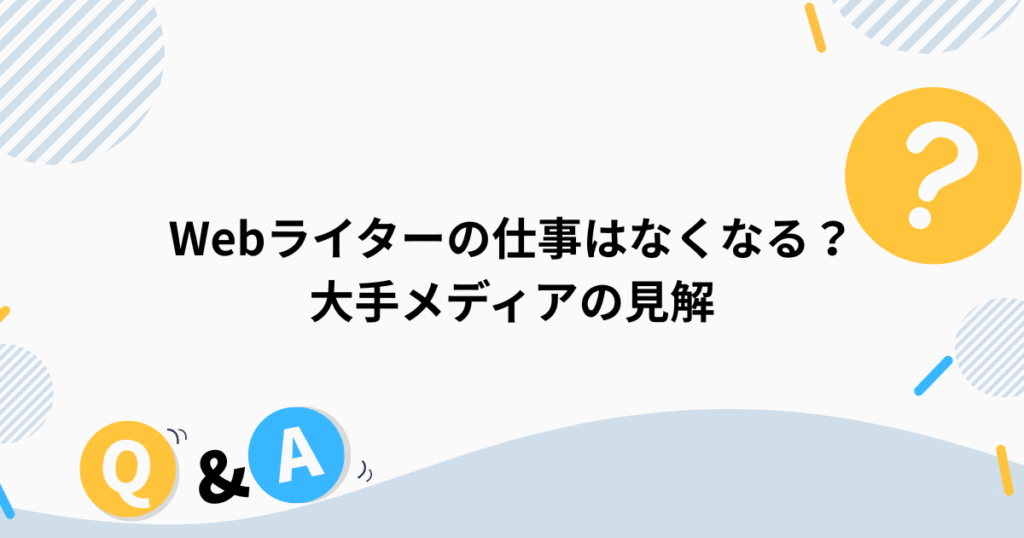
Geekly Mediaやミライトマッチなど多くのメディアで共通していたのは、Webライターの仕事は完全にはなくならないものの、一部の単純作業は少なくなるという見解でした。
生成AIが普及する前であれば、検索上位の記事をまとめて多少のオリジナリティを加えればSEOで評価される傾向にありました。
しかし、生成AIはインターネット上の情報をまとめて記事にするのが得意なので、これまでのようにインターネット上の情報をまとめるだけでは、Webライターとして生き残るのは難しいでしょう。
生成AI時代にWebライターとして生き残る方法として挙げられていたのは、以下のような方法です。
- 生成AIを活用しながら執筆作業をする
- 60〜70点レベルの記事を編集するスキル
- 感情に訴えかけるコピーライティングのスキルを磨く
- 専門性を磨いて特化ライターになる
生成AIは執筆作業の効率化に大きく貢献する反面、すでにWebライターの仕事に影響を与えているので、今後Webライターとして活動していくには工夫が求められるでしょう。
次からは生成AI時代で必要になりそうなスキルを紹介していくので、今後もWebライターとして活躍したい方は参考にしてください。
生成AI時代でもWebライターとして活躍するための差別化スキル7選
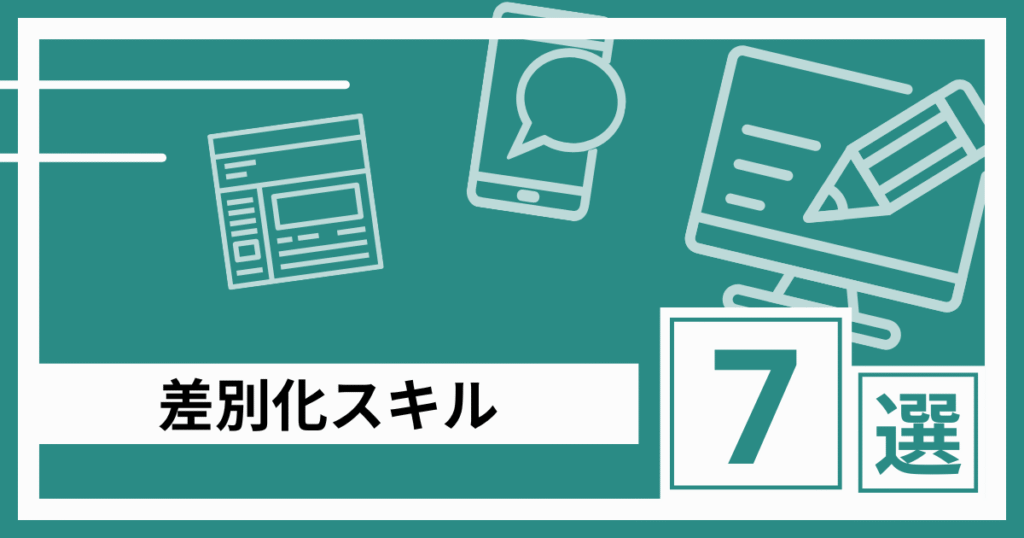
生成AIを「仕事を取りあうライバル」としてだけでなく、仕事を助けてくれる「パートナー」としても捉えることで、生成AI時代でもWebライターとして活躍できます。
生成AI時代にWebライターが身につけるべき重要なスキルは以下の7つです。
- 生成AIの活用能力
- 生成AIの文章を編集するためのライティングスキル
- 専門性の深化
- 人間らしい表現力と共感力
- 読者ニーズの徹底的な理解
- 取材するスキル
- クライアントとのコミュニケーション力
上記の多様なスキルについて、それぞれ解説します。
1. 生成AIの活用能力
生成AIツールを上手に使いこなすことは、現代のライターにとって必要不可欠なスキルになりつつあります。
他のWebライターが生成AIを効果的に使っているなかで、使わずに執筆していると、作業速度や品質の面で遅れをとってしまうからです。
クライアントから生成AIの使用許可を得られた場合は、構成の作成や執筆、ファクトチェックなど、さまざまな場面で効果的に生成AIを活用しましょう。
2. 生成AIの文章を編集するためのライティングスキル
生成AIの普及で基礎的な文章作成は自動化されつつありますが、基礎的な文章力が身についていないと、生成AIが出力した文章に問題ないか判断できません。
生成AIの普及でライティングスキルを活かす場面は少なくなることが予想されますが、生成AIが出力した文章を編集するために、基礎的なライティングスキルは必要になるでしょう。
基礎的な文章力を磨きたい方は、「新しい文章力の教室」という本がおすすめです。また、SEOの基礎知識をおさえたい方は、「沈黙のWebライティング」という本が個人的におすすめです。
3. 専門性の深化
特定の業界や分野に関する深い知識をもつことができれば、主にインターネットから情報収集する生成AIには、簡単に真似できない強みになります。
医療や金融などの専門分野を選び、知識や経験を積んだり資格取得を目指したりすることで、専門家としての視点から価値ある記事を書けるようになります。
4. 人間らしい表現力と共感力
生成AIは大量のデータを学習しているので多様な文章を生成できますが、人間のように何かを感じたり経験したりすることはできません。
そのため、実体験からのストーリーのある文章や感情に訴えかけるコピーライティング、ユニークな表現は、生成AIは苦手としています。
自分自身の体験談や感情を交えた記事は、生成AIが普及しても読者の心に響くコンテンツとなるでしょう。
5. 読者ニーズの徹底的な理解
生成AIも進化を遂げているので、読者ニーズを把握するうえで貴重な洞察を与えてくれる場合も多いですが、現状の生成AIは読者ニーズを把握するのに限界があります。
以下のように、さまざまな情報源から読者のニーズを徹底的に理解して記事に反映させることで、生成AIには難しい高品質な記事が仕上げられるでしょう。
- サジェストワード
- 再検索ワード
- 上位記事の傾向
- Yahoo!知恵袋
6. 取材するスキル
生成AIの活用が広がるなかで、他社との差別化を図るために、各メディアは「人」に焦点を当てたコンテンツを増やしています。
有名人や各分野の権威などへの取材によって得られるオリジナルの情報は、インターネット上にはない一次情報になるので、コンテンツの独自性や信頼性を高めるうえで価値が高まるでしょう。
7. クライアントとのコミュニケーション力
クライアントの要望や期待を正確に理解して記事に反映させるためには、高度なコミュニケーション能力が不可欠です。
生成AIは指示された内容に基づいて文章を生成できますが、言葉の裏にあるニュアンスやクライアントが本当に達成したい目標を読み取ることは難しい場合があります。
クライアントとの円滑なコミュニケーションを通じてニーズを的確に把握し、信頼関係を構築できれば、生成AI時代でも継続案件につながりやすくなります。


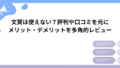
コメント